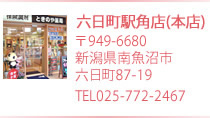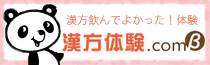排便は最大のデトックス!「元気でいたかったら腸の中をきれいに」
健康のために体に良いという食事や補助食品を摂ったり休養を取ったりしている人は少なくありません。
足りないものを補うことや弱った体質をフォローすることは必要ですがもう一つ忘れてはいけない大事なことは、体の解毒と排毒機能を高めることです。
スムーズに解毒排毒が行われていれば疲れもたまらず代謝も良くなり健康でいられます。
身体の排毒は5つのルートで行われます。
❶大腸からの排便(食毒)
❷腎臓からの排尿(水毒、尿酸など)
❸肝臓からの胆汁排泄(脂毒、脂溶性の毒)
❹皮膚からの発汗
❺子宮からの排血(月経血)
これらの正常な排泄ルートで割合が大きいのが「排便」です。
ところが便秘の方がなんと多いことでしょう。
「長生きしたかったら腸の中をいつもきれいに」という漢方の言葉があります。
「下剤を使えばいいや」という対策から「自分の腸の動きを良くして排便する」という方法に切り替えますと便通が良くなるばかりではなく体調全体が良くなります。自然のお通じを目指す場合は「肛門に溜まっている便秘」と「腸に溜まっている便秘」で対策が異なります。
また、「腸に熱がこもっている便秘」「腸の運動が怠けている便秘」「ストレスでお腹が張ってくる便秘」のタイプ別に食養生や漢方薬対策があります。
子供の成長で大切なことは生活リズムの確立
端午の節句はこどもの日。
子供たちが夢を持って羽ばたけるように健康で丈夫な体と心を作れる世の中でありたいですね。
赤ちゃんから15歳までの発育期では骨や筋肉の成長、脳の発達などのために、十分な栄養、睡眠をとり精神環境を整えることがとても大切です。
早寝早起き、生活リズム、食生活を整えることは、多忙な現代生活ではとっても大変!お子様の健やかな成長の為、ご家族皆様でチェックしてみましょう。
□食べ物の好き嫌いが多い
□朝起きて食欲がない
□朝食を摂る時間が無い
□夕食の時間が遅い
□睡眠時間が短い
□よく体調を崩す
□イライラしやすい
□便秘しがち
□おやつがお菓子や甘いものになっている
子供は活動のエネルギーの分と成長の分の栄養が必要です。
ですから3食では不足しがちなので、おやつ(八つ時の食べる食事)が必要です。
おやつでもカロリーと栄養のどちらも必要です。
おやつは主食や季節の果物などで補い、砂糖の摂りすぎには注意しましょう。
子供の成長のカギは「胃腸の強さ」にあります。
胃腸の力は植物に例えると根っこに相当します。
食べ盛りのお子様の消化吸収代謝の力を高めて効率よく栄養を摂りこめるようになると内臓が強くなり免疫力も上がってきます。
1口30回噛むこと・胃腸を冷やさない・唾液以外の液体で流し込まない・お腹を空かせる・便秘をしないことなども元気でいるための養生です。
「漢方と薬膳サロン」6月16日(日)塩沢公民館1時~3時半テーマは「便秘しない身体つくり」参加費3000円お申し込みはときのや薬局まで
春のイライラ・落ち込みにはわけがあります
枕草子の始まりは
「春はあけぼの・・・・・」ですね。
学生時代に暗唱した。という方も多いのではないでしょうか?
春はあけぼの。
やうやう白くなりゆく、山ぎはすこしあかりて、むらさきだちたる雲の細くたなびきたる。
情景が浮かびあがりますね。
さてさて中医学では「春は・・・・・・」というと「春は肝・・・」と続きます。
春は肝が頑張ります。
頑張りすぎます
負担がかかります。
ということです。
中医学漢方でいうところの「肝」とは西洋医学の「肝臓」とはちょっと違います。
「肝」は「気」の流れを調整し「血」を浄化・貯蔵し「自律神経」や感情のコントロールをしています。
ですから「肝」の調子が悪くなると
・イライラ怒りっぽくなる
・ やる気が起きない
・筋肉が硬くなる
・爪がもろくなる
・目が充血・乾燥ゴロゴロ
・便秘と下痢
・月経不順
・PMSが強くでる
・喉にものが詰まった感じ
・胸やお腹が張る
こんな症状が出やすくなります。
「青筋立てて怒っている」
「風船のように身体がパンパンに張る」
こんなイメージでしょうか。
春は「肝」の「気」が旺盛になりやすいので
その気が循環しにくくなります。
これを「気滞」と言います。
春は特にしっかり「肝」の「気」を巡らせる肝の疏泄の働きをケアしましょう。
これを放っておくと五月病へまっしぐら。
少々の「プチうつ状態」は春は誰しも感じるものだと思って深刻にならず、食べ物、ハーブ、漢方薬でフォローしましょう。
肝の気の流れを良くするものは
香りの強い野菜類やかんきつ類です。
三つ葉・セロリ・紫蘇・パセリ・バジル・セリ・・・・・
ジャスミン茶や菊花茶・・・・
グレープフルーツやオレンジ・ぶんたん・・・・
無性にセロリがボリボリ食べたくなる時ってありませんか?
三つ葉を一パック全部食べたいときはありませんか?
雪国では今、菜っ葉が盛りです。
香りのよい葉っぱが売れています。
美味しく感じる時は身体が必要としている時ですね。
食養生とともに「肝」を守る大切なことは
食休め(食べすぎず)
酒休め(アルコールをほどほどに)
目休め(パソコン・スマホを見る時間を減らす)
早めに眠る(肝・胆の時間は11時~3時)
この4つの休めが大切です。
雪国の雪囲いを外した木々のように「肝」は伸び伸びとするのを喜ぶ臓器なのです。
自然界に五臓を当てはめる「五行説」でも「肝」は「木」なのです。
本格的なうつ状態になる前に春はちょっと苦手という方
是非ご相談くださいね。
39歳、見事な摂生で自然妊娠(糖尿病・高血圧・筋腫合併)
T様、39歳、見事な自己管理で妊娠~出産を成し遂げました。
高血圧・インシュリン抵抗性糖代謝異常・肥満・粘膜下に7cmの筋腫あり。
年齢、合併症、BMI高値の事からご自分も相当心配していました。
不正出血も続いていて、婦人科での検査や治療もなさっています。
でも驚くことにFSH・LH・AMHはまだまだ若い人並みの数値です。
今の状態で妊娠してしまってはかえって、妊娠継続に不安を抱えます。
身体つくりをしてから、妊娠に耐えられるような身体を作るまで焦らず取り組みましょう。
ということで漢方薬を始めました。
やれることは全部やります!と宣言してくれました。
11時までに眠る
糖質制限しながら血糖値を下げていく
間食をゼロにして3食だけ食べる。
夕食は軽め。
砂糖・揚げ物・乳製品・加工肉は食べない。
1食で2品のタンパク質を食べる
スクワットはトイレに行くたびに10回ずつ。
1日5回はトイレに行きますから毎日50回のスクワットをしていたことになります。
お空に向かって「お~い!ここに居るよ~。早くお出で~」と叫ぶこと
全部守ってくださいました。
約8か月の服用で自然妊娠!
その間HbA1cは5.8→5.4で安心な数値に。
血圧は正常になり降圧剤は不要。
4か月の妊活漢方の服用で妊娠!
妊娠中も血糖測定毎食後。正常値
血圧も正常値
体重は1キロも増やさずダイエットしながらの妊娠生活。
でも栄養はしっかり補給していました。
何よりも心の安定が一番。
妊娠直前にはとても穏やかに、メンタルも強く、「妊娠しない気がしない」とおっしゃるほど自信に満ちてきました。
お母さんになるってそういうことだな~とこちらも感激。
産まれた赤ちゃんはお肌ツルツル、髪の毛フサフサで看護師さんの驚かれるほど。
摂生の賜物です。
赤ちゃんがほしいすべての方に
元気な赤ちゃんを産みたいと思ったら、ご自分の身体をそれなりに作り上げましょう。
チョコは止められないとか
お菓子は止められないとか
早寝ができないとか
スクワットを3日坊主で止めていますとか・・・・
摂生ができない人はまだまだ覚悟ができていないとみなします。
なかなか授からない方、Tさんを見習ってみて!
花粉症もインフルエンザも「バリア機能」アップで予防
この冬はインフルエンザ対策に明け暮れたのではないでしょうか。
これからは花粉症対策ですね。
中医学ではどちらも「バリア機能を高める」という方法で予防します。
中医学では感染症やアレルギー疾患が起こる原因を二つの方向から考えます。
一つは体表のバリア機能(衛気)が弱い場合。
もう一つは症状を引き起こす邪気(気候の変化や花粉やウィルスなど)が強い場合。
衛気とは主に皮膚や粘膜に存在する免疫パワー。
体の防衛力のようなもので、粘膜のバリアの役割を果たしています。
インフルエンザの予防のために衛気強化の漢方薬を飲み続けていたら、翌年の花粉症が発症しなかったという方がたくさんいらっしゃいます。
花粉症の症状が出てしまったら症状別に対策があります。
現代ではくしゃみ・鼻水だけではなく目の痒み・のどの痒み・咳・肌の痒みなど多岐にわたります。
水っぽい鼻水がだらだら出る時は「寒タイプ」の症状。体を温め水分代謝を良くして治します。
黄色いドロッとした鼻、のどや眼が痒い場合は「熱タイプ」の症状。
炎症を鎮めながら治します。
アトピー体質・花粉症・乾燥肌の方はこの時期に「肌トラブル」も起こしやすいものです。
今からのスキンケアとともに衛気強化の漢方薬で体質や肌体質の改善をしておきましょう。
花粉症予防の生活は11時までに眠る・冷たい物や甘いものを摂りすぎない・しっかり呼吸する・胃腸を守ることです。
バリア機能の衛気は胃腸と肺の共同作業で作られるからです。
「漢方と薬膳サロン」3/30(土)は「風邪や花粉症の漢方初期治療と免疫力」がテーマです。塩沢公民館で1時~3時半 参加費3000円 薬膳スイーツが付きます。
年末年始の胃腸疲れは舌でチェック
年末年始のお疲れが出ていませんか?
だるい・眠い・やる気が出ない・便秘や下痢などの便通異常・皮膚病の悪化・風邪が長引く・胃もたれや食欲不振・鼻の病気の悪化・口内炎など・・・
これらは中医学漢方的に言うと「胃腸の許容範囲を超えた食べ方」が原因している場合が多いです。
いわゆる食べすぎ・飲みすぎ・体に負担のかかる食べ物の摂りすぎです。
これらを舌が教えてくれます。
★舌の中央部分に白や黄色の苔が厚く付いている方。
中医学漢方の見方では苔は「消化されない老廃物が体に溜まっていますよ」というお知らせです。
夕食を軽く済ませ、デトックスのためにキャベツや白菜など葉物野菜をゆでてたっぷり食べましょう。
★舌の輪郭に歯の跡がついている方。
舌が浮腫んでお口に収めたときに歯が当たってくぼんでいます。
舌が浮腫むほど水分を摂りすぎているか胃腸が弱って水分をさばけきれずにいるのかもしれません。
浮腫んだ舌を噛んでしまうこともありますね。
体力をつけて水を巡らせる食材(豆・山芋・茸・ハトムギ)を摂りましょう
★舌の裏側に紫色の血管が浮き出てい方。
血流が悪くなっています。
こってりした食べ物やごちそう三昧の結果かもしれません。
青魚やにんにく・ラッキョウなどで血流を良くしましょう。
★舌の輪郭が真っ赤の方。
年末年始の非日常生活でストレスが溜まっているのかもしれません。
セロリ・バジル・シソなどの香り野菜でストレス発散しましょう。
★舌の色が薄い方。
血が足りない場合は健康なピンク色が淡い色になります。
舌で健康状態がわかります。
大きく体調を崩す前に舌を診て何を食べたらよいか、何を控えたらよいか見極めましょう。
「漢方と薬膳サロン」3月30日13時~塩沢公民館にて参加費3000円
「風邪を半日で治す漢方初期治療と免疫力」お申し込みはときのや薬局へ
漢方での「温活」はタイプ別に対策
寒い季節だけでなく、夏場の冷房でも悩まされる「冷え性」を放っておくと、臓器の働きが低下し頭痛・肩こり・疲労感・関節痛・生理痛・胃腸不調・免疫低下など全身の様々な不調につながります。
冷え症には症状と体質・原因別に対策があります。自分の症状や体質に合わせて取り入れることが大切です。
例えば体内の血が足りていないのに、血流を促すことばかりやっても効果は表れません。
この場合は血流改善よりもまず足りない血を増やすことが先決です。
では具体的に4タイプをご紹介します。あなたの冷えはどのタイプ?
見当違いの努力をしていませんか?
❶【気血不足の冷え】エネルギーや血が足りないために疲れて、不眠・めまい・月経時の冷えが強い。ナツメ・お肉で気血を増やしましょう。
❷【胃腸虚弱の冷え】栄養を吸収することが苦手で、温めるエネルギーを作り出すことができません。体を温め消化を促す香辛料や薬味を取り入れましょう。
❸【血行不良の冷え】運動不足・生活の不摂生・過剰なストレスなどで血流が滞りがちに。痛み・しびれを伴うことも。青魚など血流さらさら食材を。
❹【陽気不足の冷え】高齢者に多い温める力が足りないタイプ。腰痛や頻尿、浮腫み、手足が氷のように冷たく、顔色が白い。腰回りをカイロや腹巻で守りましょう。
暮らしの冷え対策もお忘れなく。3つの首(首・手首・足首)を温めて熱を逃がさないように。胃腸に入れるものは温かいものに。体を動かし陽気や血を巡らせましょう。
特に女性の冷え対策は生理や妊活や更年期のお悩みにも通じることが多いです。
初潮から閉経まで 女性ホルモンと陰陽のバランスを学んでみませんか?
ときのや薬局は薬膳食育師の仲間たちとともに「漢方と薬膳サロン」を開催しています。
女性のためのキレイと元気を作る講座です。12月は第20回目。
今回のテーマは「初潮から閉経までの体の変化と女性ホルモン」
7の倍数の年齢で変化すると言われる女性の体を、中医学漢方の見方で解説します。
年代別に注意する病気の予防のお話です。
生理痛は無いのが当たり前。
どんな時に病院での検査が必要か。
脳と卵巣と子宮の関係、一ヵ月の女性ホルモンの変化と心と体への影響。
良い生理が迎えられると身体もお肌も心も健やかになります。
痛みや辛さは問題あり!PMS(月経前症候群)はどうして起きるの?
更年期のホットフラッシュのわけは?
中医学の「陰陽のバランス」がわかると「体のなぜ?」が「なるほど!」に変わります。
今まで冷え症だった方が更年期からほてり症に変わる。
女性ホルモンの事がわかると産婦人科での先生の説明が良く理解できます。
内膜症・腺筋症・筋腫・多嚢胞でお悩みの方、妊活中の方、将来妊娠を望む方、更年期真っただ中の方、お嬢さんが初潮を迎えた方、ご参加をお待ちしています。
女性の一生は点ではなく線でつながっています。
生理痛の無い身体つくりの養生が次の年代に反映されます。
日時 12月8日(土)13時~15時半
場所 塩沢公民館2階
参加費 3000円 小中高校生は1000円 お友達割り・親子割りがあります。
お申し込みはときのや薬局までお電話で025-772-2467 薬膳スイーツの試食付き。
フレイル予防は中医学の「抗老防衰」対策で
先回は要介護や寝たきりの前段状態「フレイル」のお話でした。
フレイルの3つの側面。❶筋肉量が低下し動けなくなる肉体的フレイル
❷気力の低下による精神的フレイル
❸引きこもりや社会的な孤立といった社会的フレイル
この3つの側面が総合的に衰弱すると寝たきりなど様々なリスクが高まります。
フレイルに早く気付いて健康な状態に戻れるようにしましょう。
西洋医学や地域の取り組みもフレイル対策として重要です。
筋肉の原料となる栄養の補給・骨や関節の治療やリハビリ・運動習慣・活気に満ちた生活・ボランティア参加や高齢者の集会サロン・社会とのつながりなどの活動が盛んに行われています。
一方、中医学の世界でのフレイル対策は「健脾」「補腎」「活血」という方法です。
「健脾」とは胃腸を丈夫にして、食べた物の消化吸収率を上げ、栄養が身になる(筋肉や骨など)力をつけることです。
丈夫な胃腸があって初めてタンパク質が血となり肉となるのです。
「補腎」とはアンチエイジングの事。
「腎」とは単に腎臓の事ではなくホルモン系・カルシウム代謝・自律神経など幅広い機能を指し、生命力、免疫力、自然治癒力を支えています。
「腎」が弱ると足腰がだるい、疲れやすい、骨や歯がもろくなる、健忘、聴力低下などの症状が現れます。
「腎は骨を主り、髄を生じ、脳に通じる」という言葉で表されます。
「活血」とは血流を良くすること。
血液の粘度が高くなり、流れが悪くなった状態を改善し、きれいな血液がイキイキと全身を流れるようにすることです。
若い頃からの生活習慣、食養生、メタボ予防・ロコモ予防が将来のフレイル予防にも繋がります。
体と心と社会性をいつまでも保ち続けましょう。
「漢方と薬膳サロン」12月8日(土)1時~3時半 塩沢公民館にて 参加費3000円
「初潮から更年期までのホルモンと陰陽のバランス・冷え性からほてりへの変化」
寝たきり予防の新たなキーワード「フレイル」対策
敬老の日が過ぎました。
元気に100歳を迎える方がいらっしゃる一方で、加齢とともに弱っていく高齢者も急増しています。
現代の超高齢化社会では、高齢者の寝たきりを予防し健康長寿を伸ばすことが大きな課題となっています。
フレイルとは「健康な状態と介護が必要な状態の中間の状態」を言います。
フレイル状態では、要介護や寝たきりになるリスクが高くなりますが、今後の生活習慣の改善次第で元の健康な状態に戻れる可能性があります。
フレイルチェック(3項目以上でフレイル)
① 体重減少(半年以内に2~3キロ以上)
② 握力低下
③ 「自分が活気にあふれている」の質問に「いいえ」と回答
④ 歩行速度が毎秒1メートル未満
⑤ 外出が1日1回未満
フレイルには3つの側面があります。
筋肉量低下(サルコペニア)や歩行障害といった「肉体的フレイル」
うつ状態や気力の低下などの「精神的フレイル」
引きこもりや社会的な孤立といった「社会的フレイル」
フレイル状態ではこの3つの側面が総合的に衰弱しており、寝たきりのリスクが高まった状態にあります。
多くの方はこのフレイル状態を経て要介護に移行しますので、早く気付いて健康な状態に戻れるようにご家族や周囲の方が注意していく必要があります。
身体的フレイルは低栄養とかかわりが深く、食糧の豊富な現代にあっても、一部の高齢者は筋肉の原料となるタンパク質を充分に摂っていないことが考えられます。
筋肉をつけて運動習慣を身につけ、家族や友人とのつながりをしっかり持ち元気に長生きを目指しましょう。
次回は中医学漢方でのフレイル対策をご紹介します。